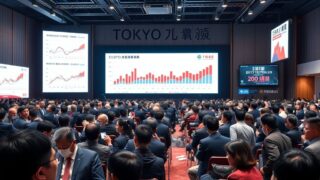概要
2021年に福島第一原発の処理水放出が始まって以来、2年が経過した。
中国は昨年、一部の37県の日本産水産物の輸入を再開し、北海道や岩手県を含む一方、宮城県や福島県など10県には引き続き輸入禁止措置を継続している。
水産業界は評判への影響を懸念しつつ、顧客回復を見込みながら、中国以外の販売チャネル開拓も進めている。
北海道・仁木のマルウロコ三和水産の社長は、中国の輸入再開が事業救済につながると期待し、約15人の従業員がホタテの殻むきを行っている。
中国の規制解除後、同社は米国向けの輸出を倍増させたが、米国の関税政策(15%関税)の影響で販売交渉は停滞している。
米国では大型ホタテを好む傾向に対し、今年は小型のホタテが獲れ、販売に影響が出ている。
輸出再開のために中国への手続きを進めているが、検査等がどれくらいかかるか不透明で、社長は中国の対応を注視している。
岩手県の宮古では、放射性物質により中国への輸出が停止されているが、代替市場としてアフリカや米国、東南アジアへの展開を模索しつつ、今年の輸出量は前年の約2倍の2,500トンとなった。
しかし中国向けの方が輸出コストが低いため、中国回復の影響は経済的に大きい。
宮城県は輸出損失の補填と新市場開拓を進めており、昨年の県産水産物の輸出額は約9.7億円と、原発事故前より5.6億円減少した。
中国向け輸出の一部再開により、宮城のホタテ価格と販売量の回復も期待される。
福島県では、放射能汚染の懸念から海藻の輸出禁止が解かれず、地元の漁師らは規制解除を願い、地方政府との交渉を望んでいる。
いわき市の企業は来年度からフラウンダーなどの加工品を中東やアジアに輸出し、地域の特産品としてのブランド向上を目指している。
ポイント
- 中国の輸入再開で北海道などの水産業が回復の兆し、輸出拡大が期待される。
- 米国の関税や規制により、日本の水産物の海外販売は依然難航している。
- 福島と宮城の水産業は新市場開拓や価格安定のため努力を続けている。
詳しい記事の内容はこちらから
参照元について