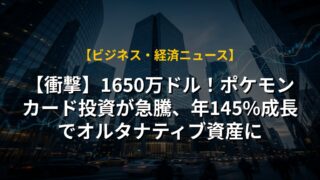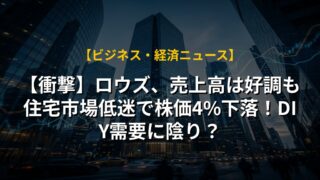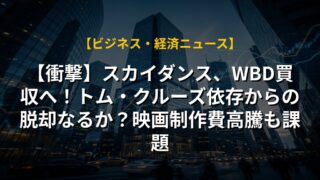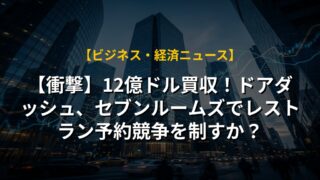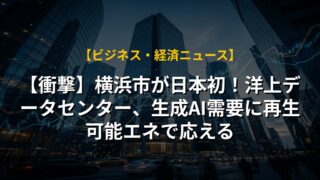財政政策と金融政策を同時に用いる現代経済における実例とその効果
財政政策と金融政策の基本的な役割と現代経済への影響
財政政策と金融政策は、現代経済において極めて重要な役割を果たしている。
財政政策とは、政府が税制や公共支出を通じて景気を調整する政策手段を指す。
これに対して、金融政策は中央銀行が金利やマネーサプライ(通貨供給量)の操作を通じて経済全体をコントロールするものだ。
両者は本来補完的な関係にあり、景気刺激や景気抑制を狙って時に同時に動くことがある。
特に大規模な経済危機に直面した際、財政政策と金融政策を同時に大胆に発動することが、実体経済の安定化に不可欠となるケースが世界中で増えている。
財政政策と金融政策の「同時」発動が注目された背景
世界経済は21世紀に入り、リーマンショックや新型コロナウイルス感染症(COVID-19)など、かつてない規模のショックを経験してきた。
このような未曾有の危機に対して、財政政策と金融政策を同時に機動的に運用することの重要性が各国で認識されてきた。
特に2020年のパンデミック発生時、各国政府と中央銀行は、従来にない規模の経済対策を迅速に打ち出した。
その代表例がアメリカ合衆国の取り組みだ。
アメリカのコロナ禍対策における政策パッケージ
アメリカ合衆国では、パンデミック発生直後、トランプ政権およびバイデン政権による大規模な財政出動と、FRB(連邦準備制度理事会)による超金融緩和策が同時に実施された。
財政政策面で言えば、2020年3月に「CARES法」が成立し、約2兆ドル(約220兆円)規模の経済対策が実施された。
個人への現金給付、失業保険の拡充、企業支援など、多岐にわたる歳出が一気に決定された。
一方、金融政策については、FRBが政策金利を一気にゼロ近辺まで引き下げ、大規模な量的緩和(QE)を再開した。
FRBは政府証券やMBS(モーゲージ担保証券)を大量に買い入れ、金融市場への資金供給を拡大したうえ、企業向けの緊急融資制度も相次いで発表している。
財政政策と金融政策が、これほど大規模かつスピーディに、同時に総動員されたのは戦後初とも評された。
財政政策と金融政策の同時発動がもたらした結果
米国の事例で顕著だったのは、財政政策と金融政策を同時導入することで、経済活動の落ち込みが想定より短期間で回復に転じた点である。
米労働省の統計によれば、2020年春には失業率が一時15%に達したが、その後2021年末には5%程度まで急速に低下した。
家計・企業・自治体のバランスシートの傷みを財政出動で支え、金融市場の動揺や資金繰り不安は超金融緩和で沈静化させた。
経済学者のジャネット・イエレン(Yellen)やポール・クルーグマン(Krugman)は、財政政策と金融政策の同時発動がこの「V字回復」をもたらした大きな要因であると論じている。
株式市場も2020年後半から2021年にかけて過去最高値を更新し、米国経済全体の回復基調への信認が広がった。
同時発動の効果と課題
財政政策と金融政策を同時に用いると、景気刺激効果が相乗的に高まるというメリットが生じる。
景気低迷下では、民間の資金需要が消極的になるため、いくら金融緩和をしてもマネーが回らない“流動性の罠”に陥ることも多い。
この場合、政府が財政出動を積極的に行い、需要喚起や所得補償を図ることで、民間の需要と投資意欲を下支えできる。
一方で、財政政策と金融政策を同時に長期運用すると、将来的な財政赤字の拡大や過度なインフレ、資産価格バブルなどの副作用も懸念される。
そのため、政策の持続性や出口戦略についても、各国の政策担当者や専門家間で議論が続いている。
先進諸国に見る同時活用の拡がり
財政政策と金融政策の同時運用は、アメリカ以外にも欧州連合(EU)、日本、オーストラリア、カナダなど先進諸国の経済運営にも広がっている。
欧州連合(EU)のケース
欧州中央銀行(ECB)は2020年3月に「パンデミック緊急資産買い入れプログラム(PEPP)」を創設し、1兆ユーロ超の債券購入で金融システムを下支えした。
これに並行する形で、欧州委員会とEU加盟国は7500億ユーロ規模の復興基金「Next Generation EU」を創設し、加盟各国向け支援を決定。
コロナ禍対応のため、財政政策と金融政策がかつてなく連携して動いた。
実際にこの政策パッケージはユーロ圏の経済回復を下支えし、PEPPの進展とともに長期金利も安定した。
日本における財政政策と金融政策の同時運用
日本銀行(日銀)は、リフレーション政策やイールドカーブ・コントロールなど、世界でも例を見ない大規模な金融緩和政策を長年にわたって続けている。
2020年からは、これに加えて政府の財政政策がより積極姿勢となり、コロナ対応で2020年度から3年連続の補正予算編成が行われた。
個人や中小企業への給付金・助成金事業だけではなく、雇用調整助成金の拡大、自治体支援など財政火力も大きく発動された。
黒田東彦(はるひこ)総裁(当時)率いる日銀の強力な金融政策と、政府の度重なる財政拡大が同時に発動されたことで、日本が比較的危機を乗り越えられたとの評価がなされた。
財政政策と金融政策の同時活用がもたらす今後の展望
歴史的に、財政政策と金融政策は意図的に距離を取って運用されることが一般的だった。
だがグローバルな経済危機やパンデミックのような異常事態には、両者の「同時」発動が経済回復のカギとなった。
今後、新たな経済ショックや気候変動対応といったグローバル課題においても、財政政策と金融政策を柔軟かつ戦略的に「同時」運用する重要性はさらに増すだろう。
また、AI・DX(デジタルトランスフォーメーション)など新たな産業投資推進のために、官民の資金投入を同時に加速させる政策設計も活発化しそうだ。
世界が注視する財政政策と金融政策の同時活用の行方
これまでの歴史や実際の各国の経験を振り返ると、財政政策と金融政策の同時発動は、シビアな危機への対応と経済回復の促進において不可欠だったことが強調される。
しかし「いつまで」「どの程度の強度で」「どのような出口で」両政策を同時運用し続けるのか、その設計・監督は今後も問われ続けるだろう。
クリスティーヌ・ラガルドECB総裁や、ジェローム・パウエルFRB議長、日本の植田和男日銀総裁といった主要中央銀行トップ、そして財務省や内閣がいかに協調してかじ取りを進めるか、世界が注目している。
財政政策と金融政策を同時に発動し、経済の安定と成長を実現できるか。
実在のリーダーたちの知見と対応力が、いま問われている。